チャイコフスキー:序曲「1812年」【名盤・おすすめ】
ウラディーミル・アシュケナージ サンクトペテルブルク・フィル 😘

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ウラディーミル・アシュケナージ サンクトペテルブルク・フィル 1996年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Vladimir Ashkenazy St. Petersburg Philharmonic Orchestra
アシュケナージさんの演奏は、讃美歌の合唱付きです。奥行きのある響きで厳かに歌われます。ひと昔前のような、ドンシャン気味の演奏ではなく、現代的な演奏だと思います。出典:YouTube Tchaikovsky: Overture 1812, Op. 49 – Choral version サンクトペテルブルク室内合唱団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
ロリン・マゼール バイエルン放送交響楽団 🥰

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ロリン・マゼール バイエルン放送交響楽団 1995年
ガルミッシュ山岳第1軍楽隊 Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Lorin Maazel Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks
マゼールさんの演奏は、戦争をテーマにした楽曲を集めたもので、ホンモノの大砲が使われています。ぐわん~っとぶっ放すタイプのもので、怖ろしい音圧が収録されています。これが、なんだか右と左のスピーカーから飛び出してくるので迫力があります。演奏自体は、もちろんキリリと引き締まった精緻なもので大まじめです。単なる娯楽にならないところが流石です。で、マゼールさんの演奏には、1981年ウィーン・フィル(レーベル:SC ソニー)との演奏もありますが、YouTubeには掲載されていないようでした。
CDカップリング:チャイコフスキー イタリア奇想曲、序曲1812年、ベートーヴェン ウエリントンの勝利、またはヴィットリアの戦い、リスト 交響詩フン族の戦い 出典:YouTube Overture 1812, Op. 49, “Ouverture solennelle”
ロリン・マゼール – トピック Provided to YouTube by RCA Red Seal
クラウディオ・アバド ベルリン・フィル

チャイコフスキー:序曲「1812年」 クラウディオ・アバド ベルリン・フィル 1995年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Claudio Abbado Berliner Philharmoniker
CDカップリング:チャイコフスキー 幻想曲テンペスト 1994年、スラヴ行進曲1995年、ロメオとジュリエット1996年、序曲1812年 1995年 テンペストとロメジュリはライブ録音です。出典:YouTube Tchaikovsky: 1812 Overture, Op. 49, TH 49 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
ユーリ・シモノフ ロイヤル・フィル

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ユーリ・シモノフ ロイヤル・フィル 1994年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Yuri Simonov Royal Philharmonic Orchestra
出典:YouTube 1812 Overture in E flat, Op. 49 – 1812 Overture ユーリ・シモノフ – トピック Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
ヴァレリー・ゲルギエフ マリインスキー劇場管弦楽団

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ヴァレリー・ゲルギエフ マリインスキー劇場管弦楽団 1993年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Valery Gergiev Mariinsky Orchestra Royal Dutch Marine Band
出典:YouTube Tchaikovsky: Ouverture solennelle “1812,” Op. 49 ヴァレリー・ゲルギエフ – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
エフゲニー・スヴェトラーノフ ロシア国立交響楽団 😘

チャイコフスキー:序曲「1812年」 エフゲニー・スヴェトラーノフ ロシア国立交響楽団 1992年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Evgeny Svetlanov State Symphony Orchestra of Russian Federation
スヴェトラーノフ盤と言えば、爆演だと思いこんでいたが、相当にイメージが異なる。残響が少し多めであるため、柔らかいソフトタッチに仕上がっている。ロシア正教会の讃美歌「神よ汝の民を守れ」から引用されたという、和音の美しいフレーズは、まるでオルガンで奏でられているかのようで、かなり荘厳な空気感が漂っている。実際には、チェロとヴィオラなのだが・・・ その響きが柔らかく、フルートが雲のように乗っかってくる。
信じられないほど、敬虔な雰囲気だ。「ふぁふぁそ~そら~ ふぁふぁそらししし~ ららららら~ らーららそ」その後、主題が変わるが、まだ暗鬱とした空気に支配されており、中音域の弦の響きが、かなり豊かに響いている。金管のフレーズは、ストレート気味だし、細めに聞こえるが、コントラバスの響きが大きく、当時の世情を映し出しているようだ。
ナポレオンのフランス軍のラ・マルセイエーズが、遠くから、「たらら~ららら~らったたぁ~」と奏でられるが、ノー天気には奏でておらず、充分な距離感も感じられる。木管や弦で、うろたえているような雰囲気を出しているし、シンバルが激しく鳴る。小太鼓の鳴りっぷりも良い。騎兵隊の雰囲気も出てるし、当時の戦闘の生々しさが、ソフトに描かれている。ホルンによる主題の変化が、柔らかく告げられている。「それ~ どしられれ~ られ~れ~ どしられれ~」
牧歌的というだけでなく、まるで天上の音楽に聞こえるほどで、これには驚かされた。ホントは、地味で土臭いフレーズなのだ。で、また戦闘が起こってきたようで、火だねが耐えていなかったらしい。激しく打ち鳴らされるシンバル、駆けめぐる弦。金管の咆吼が続く。再度、牧歌的なフレーズが表れ、また戦闘・・・ ダメ押しのように大砲が撃たれる。ここでは、キャノン砲ではなく、大太鼓が打たれているのだと思う。全合奏で、山をくだってくるような、テンポを落としてくだってくるようなフレーズがあり、カリヨンが打ち鳴らされる。まるで、カリヨンは蝶々のように舞っている。最後の一音が、すご~く長くて、ここだけはいただけないんだけど。まっ。許せるか~
演奏も良いのだが、録音が絶品だと思う。ホールトーンの豊かさと、距離感が感じられ、バンダ部分の音響も抜群である。想像していたほどには、派手さはないが、力強さもあり、ソフト感もある演奏だ。かなり聞きやすく心地よい。1812年で、心地良いとか、微妙なニュアンスがあって~などと言うと、変な感じがするのだが、大々的に、そして圧倒的に、単純に、勝利を祝うという雰囲気ではない。祝祭的な雰囲気は残しつつも、品よく仕上がっているような感じで、この点、ショルティ盤とは大きく異なっており、エンターテイメントな演出よりは、自国の楽曲として誇りを持って演奏している印象を受けます。
CDカップリング:チャイコフスキー 交響曲第1番「冬の日の幻想」、序曲1812年
出典:YouTube チャイコフスキー:序曲「1812年」作品49
ロシア国立交響楽団 – トピック Provided to YouTube by CANYON CLASSICS
クラウディオ・アバド シカゴ交響楽団 😘

チャイコフスキー:序曲「1812年」 クラウディオ・アバド シカゴ交響楽団 1990年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra
録音状態は、まずまず。スピードがあり、さっぱりスマート系 冒頭、チェロとヴィオラで奏でられるロシア正教会の讃美歌が、静謐に流れてくる。美しいヴィブラートがかかっており、教会音楽そのものに感じられる。大太鼓が鳴らされたあとも、スマートに、余分なモノをそぎ落とした感じで、スピーディに流れていく。テンポは、とても速い。ショルティ盤と同じシカゴ響なのだが、ブラス部分は、驚くほど分厚い響きを持っているものの、結構、速いテンポで展開するので、びっくり。主題の変わる際、ホルンには、しっかり和音を吹かせている。また、メリハリがついているので、主題が変わるところがわかりやすい。
牧歌的・歌謡風フレーズが、大変美しく奏でられている。郷愁を誘うフレーズで、戦闘シーンの激しいフレーズとの対比が、くっきりしている。大砲の音の5連発もすごいっ。キャノン砲の本物だと思う。カリヨンの乱れ打ちも凄いし、オケの音が消えそうなぐらい激しく打ち鳴らされている。基本的には、ショルティ盤と変わらないが、最後のコーダに至るまでのスピードの落ち具合も、タメず、すんなり駆け抜けていく。とにかく、スピーディでスマートって感じの演奏です。インデックスが区分されているのは、ちょっと~ いただけません。
CDカップリング:チャイコフスキー交響曲第3番、序曲1812年 出典:YouTube 1812 Overture, Op. 49, TH 49
シカゴ交響楽団 – トピック Provided to YouTube by Sony Classical
ユーリ・テミルカーノフ レニングラード・フィル

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ユーリ・テミルカーノフ レニングラード・フィル 1990年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Yuri Temirkanov Leningrad Philharmonic Orchestra
出典:YouTube 1812 Overture, Op. 49, TH 49 ユーリ・テミルカーノフ – トピック Provided to YouTube by Sony Classical
ウラディーミル・フェドセーエフ モスクワ放送交響楽団

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ウラディーミル・フェドセーエフ モスクワ放送交響楽団 1989年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Vladimir Fedoseye Moscow Radio Symphony Orchestra
出典:YouTube 1812 Overture, Op. 49, TH 49 モスクワ交響楽団 – トピック Provided to YouTube by Believe SAS
ネーメ・ヤルヴィ エーテボリ交響楽団 😘
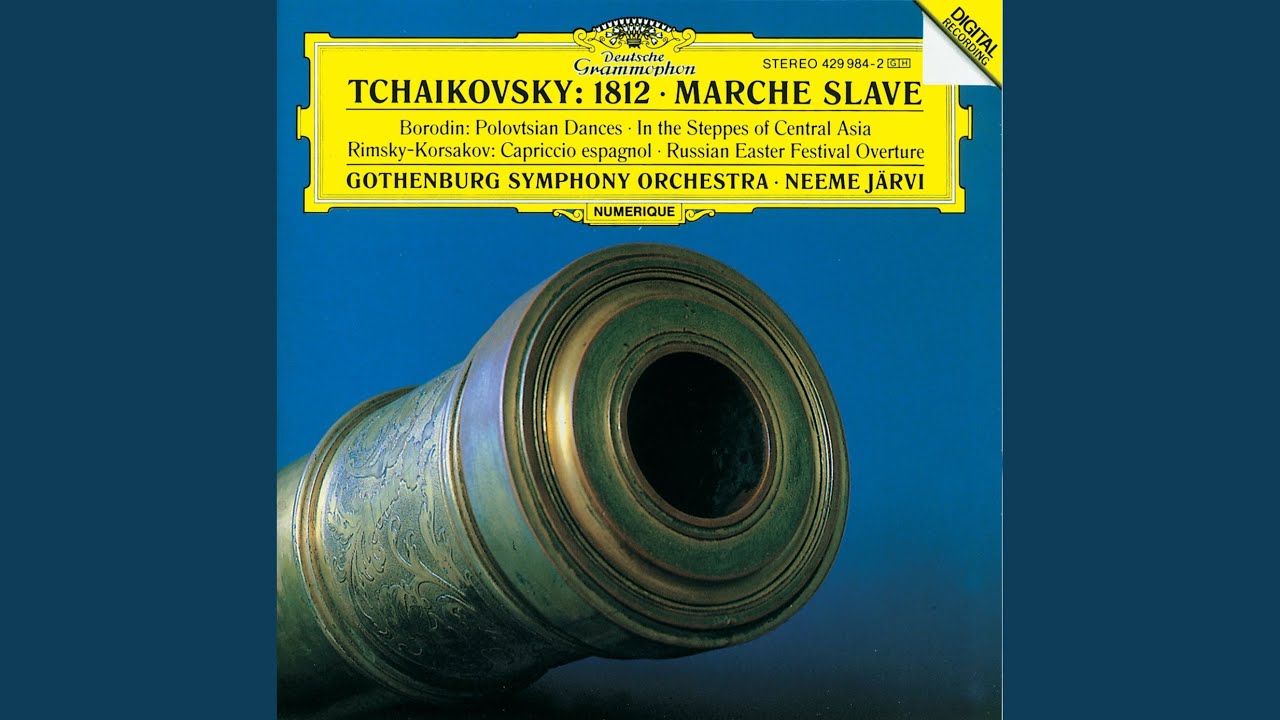
チャイコフスキー:序曲「1812年」 ネーメ・ヤルヴィ エーテボリ交響楽団 1989年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Neeme Järvi Gothenburg Symphony Orchestra
N・ヤルヴィさんの演奏は、コーラス入りの演奏です。最初の部分で合唱が入ってきます。オケの方は弦の鋭いボーイングで、スイスイと進みます。チューバの力強い響きもあって良いですね。カノン砲については軽めの音ですがリアル感があります。スウェーデンのゴータ砲兵連隊(Gothenburg Artillery Division)の実射音みたいですね。教会の鐘も、あらま~ いっぱい大きな音でガンガン入ってくるし、コーラスにバンダも入ってきて、かなり豪勢な経費のかかってそうな演奏です。ラストの音をぐいーっと大きく伸ばして終わります。やっぱり粘りますね。
出典:YouTube Tchaikovsky: Overture 1812, Op. 49, TH 49 エーテボリ交響楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
ゲオルク・ショルティ シカゴ交響楽団 🥰

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ゲオルク・ショルティ シカゴ交響楽団 1986年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Georg Solti Chicago Symphony Orchestra
序曲1812年では、本物の大砲が収録されていることで有名な盤である。もちろん迫力満点で、録音状態も極めて良い。 冒頭、チェロとヴィオラで奏でられるロシア正教会の讃美歌「神よ汝の民を守れ」から引用されたという、和音の美しいフレーズが、厳かに流れる。「ふぁふぁそ~そら~ ふぁふぁそらししし~ ららららら~ らーららそ」
ここは、さすがにショルティ盤でも、深々と悲しげに奏でられている。まるで溜息をつくようなフレーズが続いて、大太鼓の一発。「し~ららら れっ し~られみふぁみれしら~」コントラバスの低弦が蠢き、オーボエが悲しげなフレーズを奏で始めて主題が変わる。激動の嵐の様相を見せたあと、チューバを主体とした重々しいフレーズが続き、激しさを増していく。この立ち上がりは、パワフルで圧倒される。まず、ナポレオンのフランス軍のラ・マルセイエーズが、「たらら~ららら~らったたぁ~」次にロシア軍との攻防が始まる。フレーズが散り散りになっているので、フランス軍がダメージを受けているのだろう。このあたりの攻防は、ショルティ盤では、さすがにエキサイトしている。で、どうやら撃退したらしい。ホルンの平和と告げる和音が穏やかに吹かれる。
「それ~ どしられれ~ られ~れ~ どしられれ~」静かながらも甘く美しいフレーズが続く。ここは、のびやかに歌ってシアワセ感が味わえる。地味なフレーズではあるが美しい。ゆったりと牧歌的なフレーズを歌っている。再度、フランス国歌が流れてくる。また戦争かと身構えるが、再度撃退。「それ~ どしられれ~ られ~れ~ どしられれ~」歌謡風のフレーズを挟んで、また戦闘が続いて、大砲が5発。その後、全合奏的に「どしらそ しらそふぁ」と下ってきて、テンポを段々遅くしてくる。くだりきったところで、カリヨンが荘厳に鳴らされる。全国一斉、ロシア国中のあちこちの教会で、鐘が鳴らされているかのような乱れ打ち。「どふぁそらそふぁそ らふぁふぁ~」・・・「どーれれ どらふぁ ふぁみれどれ しどら・・・」←大砲打ちっ放し。まあ~ 絢爛豪華 このうえなく壮大に終わる。あっぱれ!
CDカップリング:チャイコフスキー「ロメオとジュリエット」、「くるみ割り人形」、ジェリー・ダウンズ「がんばれ、シカゴ・ベアーズ」、アメリカ国歌、スーザ「星条旗よ永遠なれ」 チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」とカップリング場合もあります。出典:YouTube Tchaikovsky: 1812 Overture, Op. 49, TH 49 シカゴ交響楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
シャルル・デュトワ モントリオール交響楽団 🤣

チャイコフスキー:序曲「1812年」 Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49
シャルル・デュトワ モントリオール交響楽団 1985年 Charles Dutoit Orchestre Symphonique de Montreal (Montreal Symphony Orchestra)
デュトワさんの演奏は、シンセサイザーが使われているということで有名です。冒頭は、意外と神妙に室内楽を聴いているような感じです。テンポをゆったり、木管、弦を重ねて、ぐぐ~っと力強い金管が合流します。雰囲気がいっぺんして華やかで馬力が出てくるという演出です。「ラ・マルセイエーズ」が、まろやかに響き渡り、当然ながら、フランス軍びいきです。颯爽と軽やかに、煌びやかに進んでいきます。歌謡風の旋律は、甘く美しく歌います。
カノン砲は・・・・ 大砲が5発鳴るはずですが、正直言ってショボイ! 拍子抜けするほど、シンセサイザーの軽い音が入ってきます。遠くで花火が打ち上がっているかのようなボコボコ音。もう一つのチェックポイント、鐘の音は、いっぱつ「ごぉ~~ん」と響きます。これは本物らしい。そこに、数多くの鈴の音のような、カリヨンの音が重なってきます。超高音のキンキン音が重なって狂喜乱舞状態の祝祭感です。
大砲はシンセサイザーで、鐘は本物の音という組み合わせ。モントリオールにあるノートルダム寺院、ケベックにある聖アンナ寺院の鐘を使っての「ぼ~ん ぼ~ん」と鳴る鐘は、とってもリアルですが、はあ? 大砲はシンセサイザーで、う~ん。なんともいやはや。オケは、文句のつけようもない美音で流麗。音響のバランスも良いのですが、異色の取り合わせオプションには、のけぞって(笑いをこらえて)驚かされました。
CDカップリング:チャイコフスキー「スラヴ行進曲」ムソルグスキー「展覧会の絵」交響詩「はげ山の一夜」
出典:YouTube Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 モントリオール交響楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
レナード・バーンスタイン イスラエル・フィル

チャイコフスキー:序曲「1812年」 レナード・バーンスタイン イスラエル・フィル 1984年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Leonard Bernstein Israel Philharmonic Orchestra
出典:YouTube Tchaikovsky: 1812 Overture, Op. 49 Leonard Bernstein Provided to YouTube by Universal Music Group
小澤征爾 ベルリン・フィル

チャイコフスキー:序曲「1812年」 小澤征爾 ベルリン・フィル 1984年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Seiji Ozawa Berliner Philharmoniker
出典:YouTube Tchaikovsky: Overture 1812, Op. 49 – Largo – Allegro giusto
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
ダニエル・バレンボイム シカゴ交響楽団
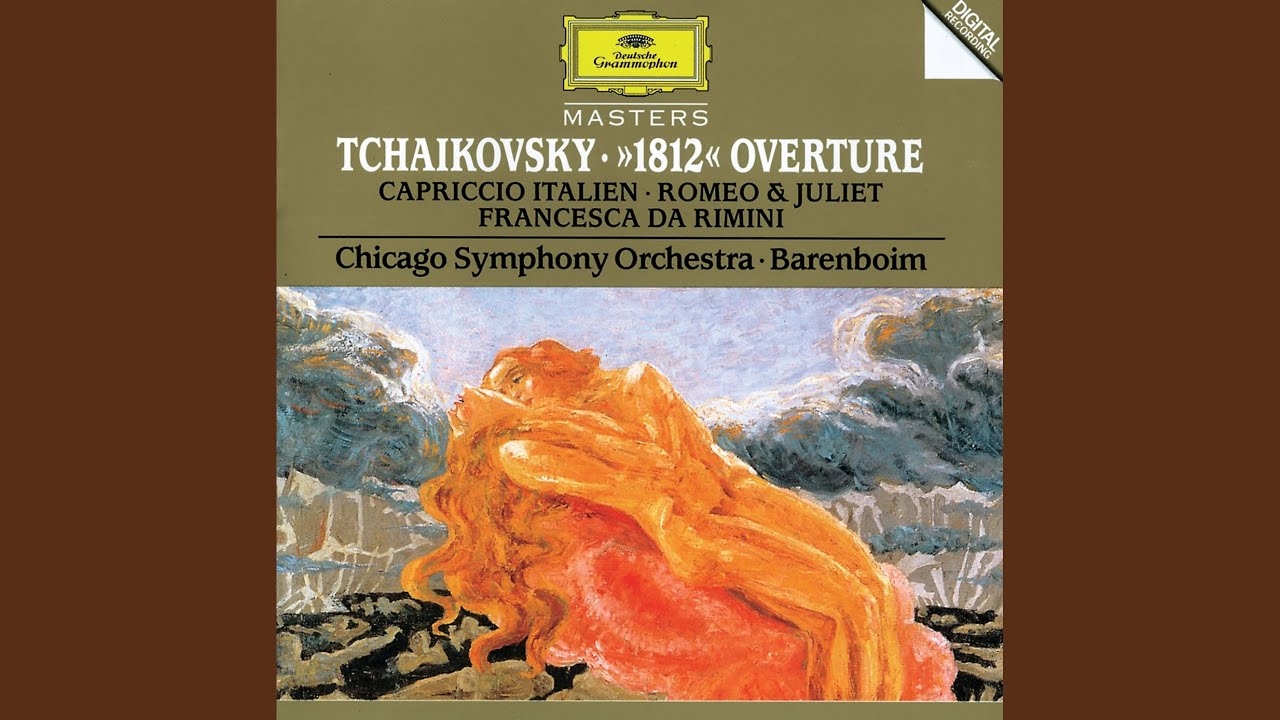
チャイコフスキー:序曲「1812年」 ダニエル・バレンボイム シカゴ交響楽団 1981年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra
CDカップリング:チャイコフスキー 幻想序曲ロメオとジュリエット、フランチェスカ・ダ・リミニ、イタリア奇想曲、序曲1812年 1981年録音 出典:YouTube Tchaikovsky: Ouverture solennelle “1812,” Op. 49
シカゴ交響楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
リッカルド・ムーティ フィラデルフィア管弦楽団 🙂

チャイコフスキー:序曲「1812年」 リッカルド・ムーティ フィラデルフィア管弦楽団 1981年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Riccardo Muti Philadelphia Orchestra
ムーティさんの演奏は、アクセル、ブレーキの効きが抜群で~ メチャクチャ熱い演奏です。録音状態はイマイチなのですが、やっぱり伊達男は違いますね。ど派手~っ! メリハリがあり、うはは~っ。序曲1812年の冒頭は、ロシア正教の讃美歌です。で、主題が変わり、オーボエが切ないフレーズを吹いた後、渋くて泣きが入ってきます。
そして、フランス国歌が流れてくると、弦がブチ切れた感じで、一気にギアがトップに入って加速していきます。ムーティさんのチェンジの切り替えの速いこと。アクセルを、ばんっと踏んづけて、ぐい~っ! 後ろにはりつくほど一気加勢に走ります。で、ブレーキを踏んだら、前につんのめってフロントガラスに、頭をぶち当てるほど。
大砲は音圧を感じます。カリヨン(鐘)は超ド派手です。速い、熱い、派手と三拍子揃っています。車で例えると、イタ車のスポーツカーでしょうか。難点は録音状態です。
CDカップリング:ストラヴィンスキー「火の鳥」、ムソルグスキー(ラヴェル編)組曲「展覧会の絵」、チャイコフスキー 序曲1812年 R・コルサコフ シェエラザードとのカップリングされたCDもあります。EMI原盤のブリリアント(Brilliant Classics)レーベルによる交響曲全集(7枚組)出典:YouTube 1812 Overture, Op. 49 チャンネル:リッカルド・ムーティ – トピック Provided to YouTube by Warner Classics
エリック・カンゼル シンシナティ交響楽団 😅


チャイコフスキー:序曲「1812年」 エリック・カンゼル シンシナティ交響楽団 1978年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Erich Kunzel Cincinnati Symphony Orchestra
★ 下のYouTubeの動画は、1999年再録 コーラス入りです。Kiev Symphony Chorus Children’s Choir Of Greater Cincinnati
カンゼルさんの演奏は、大砲の音源が入っていることで有名なものです。ワタシが所有しているCDは、1978年録音のものです。奥行きがあり少し残響多めですが、大砲が発火した途端、椅子から転がり落ちそうになるような強烈な音が入っています。大型スピーカー向けなのですが、大砲の実音はやはりスゴイ迫力があります。
冒頭は、チェロとヴィオラ、コーラスでロシア正教会の讃美歌が甘く流れてきます。ティンパニの一発後、主題が変わり激動の嵐かと思ったのですが、低弦が蠢かず、演奏自体は薄味となっています。立ち上がりの勢いがなく、戦闘態勢という感じから遠く、フランス軍のラ・マルセイエーズが、「たらら~ららら~らったたぁ~」と鳴るのですが、いたってのんびりムードで戦争という雰囲気がしません。素朴で平和的、牧歌的な中間部の後、戦闘が再開され、「タタタ タータタン~」で大砲が五発。
録音レベルは低めだったため、当初はボリュームを上げて聴いていたのですが、砲弾の音がリアルで、発火した途端、ボムっと広がります。大砲の筒の近くにマイクがあるのかもしれません。ドーンと鳴るのではなく、ぶばっ! 筒から吹き出してくる圧力がリアルです。大砲が放物線を描いて落ちるっていうのではなく、筒から出てくる破壊エネルギーが発射されています。スピーカーから、黒い玉の砲弾と共に火薬臭い噴煙が漂ってきそう。遠いところで爆発した後、波動弾が飛んできて、窓ガラスが飛び散るって感じでしょうか。
まあ。演奏自体は、たいしたことはないと言っちゃ~怒られるかもしれませんが、ハイ、娯楽的要素で楽しんでくださいというものです。大砲の音以降、極端にテンポが落ちており、くだりきってから、カリヨン(鐘)が鳴ります。この音の方が驚異的で、残響がすごすぎ~ アタマがクラクラします。鐘が何個鳴っているのか想像できません。それも鳴り響くテンポが速く、これこそ乱れ打ちという状態です。頭のうえに鐘を被らされた拷問で、グワングワン~キンキン~カンカン~シャンシャン~カシャカシャ~ で、また再度、大きくてリアルな大砲が鳴り出すという結末です。
CDカップリング:チャイコフスキー序曲1812年、イタリア奇想曲、歌劇「マゼッパ」~コサックの踊り~
CDカップリング:チャイコフスキー 序曲1812年、歌劇エフゲニー・オネーギン ポロネーズ、イタリア奇想曲、スラヴ行進曲、エフゲニー・オネーギン ワルツ、戴冠式祝典行進曲、歌劇マゼッパ コサックの踊り(最近のCD)
出典:YouTube Tchaikovsky: 1812 Overture, Op. 49 エリック・カンゼル – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
アンドレ・プレヴィン ロンドン交響楽団 😘

チャイコフスキー:序曲「1812年」 アンドレ・プレヴィン ロンドン交響楽団 1971年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 André Previn London Symphony Orchestra
プレヴィンさんの演奏は、静かに始まり、強引にど派手に終わる演奏はなく品のある演奏です。爆演を期待していたら裏切られますが、これが普通なのかもしれません。出典:YouTube 1812 Overture in E-Flat Major, Op. 49 アンドレ・プレヴィン – トピック Provided to YouTube by Warner Classics
ズービン・メータ ロサンゼルス・フィル 🤩

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ズービン・メータ ロサンゼルス・フィル 1969年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Orchestra
メータさんの演奏は、かなりの重低音で音圧を伴って響きます。序曲1812年は、大砲の音がどんな風に録音されているのか興味津々で、聞き比べのために、複数のCDをせっせと購入していました。えへへ~ ミーハーだったのです。
今の時代のように、イヤフォンを耳に突っ込んで聴くというのではなく、音響システムを構築してたし、うれしがって聴いてましたね。で、メータさんの演奏は、さすがに古めかしく、人工的に聞こますが、大砲の音は、鼓膜が心配なので、音量は調節して聴いてください。(申し上げましたよん)
12:00以降、大砲と鐘がけたたましく鳴ります。序奏部分が終わった後、ドスンっという一発入ったところで、ぐぐーっと異様に音量があがり、迫力が増します。若い頃のメータさんには、勢いがあって、ジャンジャン鳴らしていたように思います。金管は、ロス・フィルのカラフルな音で、のびやかに演奏されています。大砲は、本物をぶっ放しているのだそうです。まるで、モノが裂けるかのように響きます。
また、カリオン(鐘)も、贅沢に多数使われているようで、いったい何個鳴っているんだぁ~っと叫びたくなるほど、けたたましい響きです。キンキンの音で、目がチカチカしそうなほどうるさいです。当時の最新の合成成果なのだと思います。今となっては笑いたくなるほどの、やりすぎ、マシマシ具合です。とんでもト盤だと思いますが、当時は、メチャメチャ歓喜の声を上げて聴いていたので、この演奏を悪く言えません・・・ あしからず。ハハハ~ 聴く時は、音量に気をつけてください。
CDカップリング:チャイコフスキー序曲「1812年」1969年、スラブ行進曲1972年、幻想序曲「ロメオとジュリエット」1969年、イタリア奇想曲1980年 イスラエル・フィル 出典:YouTube Tchaikovsky: Ouverture solennelle “1812,” Op. 49 LA Phil Provided to YouTube by Universal Music Group
ヘルベルト・フォン・カラヤン ベルリン・フィル 😨

チャイコフスキー:序曲「1812年」 ヘルベルト・フォン・カラヤン ベルリン・フィル 1966年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker ドン・コサック合唱団 Don Kosaken Chor
カラヤンさんの演奏は、合唱付きです。珍しい演奏なので昔にCDを買い求めたもの。ロシア正教会の賛美歌「神よ汝の民を守れ」から引用されており、ドン・コサック合唱団の歌声が入っています。切れ味のあるスピーディで、超格好の良さが感じられます。録音状態はイマイチながら、金管のパッパら パパっ パァ~っと、短いパッセージが続くところや、弦の強奏も優美な曲線を描き、超快速で一気に駆け抜けていきます。
風を切る弦、煌びやかな切れ抜群の金管、オケ全体が、スタイリッシュな体躯をしています。録音年の古いモノなので、お薦めはできませし、最大の見せ場である大砲の鳴りっぷりは、大型の筒から空気が漏れた~って感じで、へ???? ちょっとマヌケた感じなのが、オチとなっています。ぼむっ!と、前に飛び出したというのではなく、金属音を立てて何かが横を通過していったというような感じです。
それよりも鳴りっぱなしの鐘(カリヨン)の方が、すごい強烈です。ぐわんぐわんぐわん~っ、強烈な共鳴音で、甲高く鳴り響きます。がしゃん ぐしゃん ぶわん、ぼわん ちゃらん きらん・・・。クラッシュしているかのようで、ずーっと鳴りっぱなしです。地獄で鐘が鳴り響き、拷問を受けている感じで苦痛です。もう~ ヤメテぇ~ イヤフォンで聴くのは、ちょっと~ お薦めしかねます。出典:YouTube Tchaikovsky: 1812 Overture, Op. 49, TH 49 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
イーゴリ・マルケビッチ コンセルトヘボウ管弦楽団 😨

チャイコフスキー:序曲「1812年」 イーゴリ・マルケビッチ コンセルトヘボウ管弦楽団 1964年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Igor Markevitch Royal Concertgebouw Orchestra
マルケビッチさんの演奏は、さすがに古めかしく録音なので、あまりお薦めはできないのですが、冒頭よりゴリゴリと枯れた悲痛なチェロが鳴り、ロシア正教の讃美歌のフレーズは、既に戦争に負けて死者を弔うような悲痛さがあります。それでいて、続く畳みかけてくる「たらら ららら ラッタッタ~」での鋭さは空前絶後。音が悪いのに、スピードあふれる鋭い弦の擦れた響きに、のけぞってしまいます。金管が大活躍するシーンでも、弦が怒濤のごとく弾きまくっています。マルケビッチさんの演奏だと大砲なんて要らないです。気迫で勝負ってところで、破裂音が凄まじく、シンバルのシャンシャン音が入り乱れ、これらが狂気じみてくるほど恐ろしいパワーがあります。すごみがあるって感じ。
録音状態が悪いだけに、薄気味悪いし、タイトな響きが悲愴感が漂わせます。カリヨンが鳴り響く前の雪崩落ちするところも、これ、ホントに、コンセルトヘボウなの? 木質的で柔らかい美しいオケだったなのに、なんてこったい。狂気じみており、大太鼓が入ってくるところは、音が硬く、ダダダダ ダダダダ ダダダダ・・・重い重い。がーん がーん がーーーーーんっ。ひぇぇ~! 序曲「1812年」の聴き比べは、完全に娯楽的に聴いていたのですが、クソマジメで、カッシカシに厳格で、お遊びモードは皆無の演奏でございます。特段、奇をてらった演奏をしているわけでもなく、大砲付きの演奏でもないのですが、かくしゃくとした大じいさんに雷を落とされた気分でした。
CDカップリング:チャイコフスキー交響詩集 幻想曲「運命」インバル/フランクフルト放送響 1974年、「フランチェスカ・ダ・リミニ」マルケビッチ/ニュー・フィルハーモニー1967年、幻想序曲「ハムレット」マルケビッチ/ニュー・フィルハーモニー 1967年、序曲「嵐」インバル/フランクフルト放送響1974年、幻想曲「テンペスト」インバル/フランクフルト放送響1974年、交響的バラード「地方長官」インバル/フランクフルト放送響1974年、幻想序曲「ロメオとジュリエット」ハイティンク/コンセルトヘボウ1964年、序曲「1812年」マルケビッチ/コンセルトヘボウ1964年録音
アンタル・ドラティ ミネアポリス交響楽団

チャイコフスキー:序曲「1812年」 アンタル・ドラティ ミネアポリス交響楽団 1958年
Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.49, TH.49 Antal Doráti Minnesota Orchestra University Of Minnesota Brass Band
出典:YouTube Tchaikovsky: 1812 Overture, Op. 49 ミネアポリス交響楽団 – トピック Provided to YouTube by Universal Music Group
チャイコフスキー:序曲「1812年」【解説】
チャイコフスキーの序曲1812年は、1880年に演奏会用序曲として作曲されています。ナポレオンのロシア遠征が行われた年が1812年であり、産業博覧会の際の序曲として依頼された仕事だったようです。構成としては五つの部分で出来ています。
第1部 ヴィオラとチェロで正教会の聖歌「神よ汝の民を救い」の序奏です。合唱に置き換える演奏もあり、チェロとコントラバスで第1主題が奏でられます。
第2部 ロシア軍の行進の部分で、ティンパニの弱いトレモロ、低音楽器、小太鼓が主題を引き継ぎ、盛りあがります。
第3部 ボロジノ地方の民謡に基づく主題に続いて、フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の旋律をホルンが演奏します。激しい咆哮が終わると、緩やかな第2主題に引き継がれ、ロシア民謡風の主題が現れます。再び、ラ・マルセイエーズの主題が、各パートを転々としながら演奏され、コルネット、トロンボーンが奏でられ、各楽器が咆哮します。大砲が5回鳴った後は、雪崩落ちる感じです。
第4部 第1部冒頭の主題が堂々と演奏されます。ロシア正教会のカリヨン(鐘)が打ち鳴らされます。
第5部 全楽器が強奏して、ロシア帝国国歌がバスーン、ホルン、トロンボーン、チューバ、低音弦楽器で演奏されます。鐘と大砲も豪快に鳴らされて終息します。なんだか、うーん。まっ、チャイコの一つの作品として客観的に聴いても良いと思いますが、当初の目的である産業博覧会は開催されず、後年、ピアノソロ版、ピアノ連弾版の楽譜が出版されています。なお、詳細については、Wikipediaをリンクしておきますので、ご参照ください。
チャイコフスキー:序曲「1812年」【ディスク情報】
1958年 ドラティ ミネアポリス交響楽団 MERCURY
1964年 マルケヴィッチ コンセルトヘボウ Ph
1966年 カラヤン ベルリン・フィル G
1969年 メータ ロサンジェルス・フィル Dec
1971年 プレヴィン ロンドン交響楽団 EMI
1978年 カンゼル シンシナティ交響楽団 TELARC
1981年 ムーティ フィラデルフィア管弦楽団 EMI
1981年 バレンボイム シカゴ交響楽団 G
1981年 マゼール ウィーン・フィル SC
1984年 小澤征爾 ベルリン・フィル EMI
1984年 バーンスタイン イスラエル・フィル G
1985年 デュトワ モントリオール交響楽団 Dec
1986年 ショルティ シカゴ交響楽団 Dec
1987年 N・ヤルヴィ エーテボリ交響楽団 G
1989年 フェドセーエフ モスクワ放送交響楽団 VICTOR
1990年 テミルカーノフ レニングラード・フィル R
1990年 アバド シカゴ交響楽団 SC
1992年 スヴェトラーノフ ロシア国立交響楽団 CANYON
1993年 ゲルギエフ マリインスキー劇場管弦楽団 Ph
1994年 シモノフ ロイヤル・フィル RPO
1995年 アバド ベルリン・フィル G
1995年 ロリン・マゼール バイエルン放送交響楽団 R
1996年 アシュケナージ サンクトペテルブルク・フィル Universal

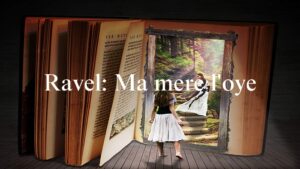






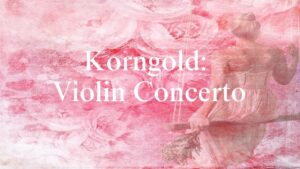


コメント